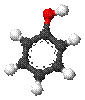
��ł̉������@�̖͍�
���R�͔|�ɏo����Ă��炢���l���Ă���̂́A�y�̎��ł��B
�y�𒆐S�ɑ傫�ȖڂŌ��悤�ƓV�̂̉e���Ȃǂ�ǂ������Ă��܂����B
���s���āu�y�Ƃ́H�v�Ƃ������Ƃ��l���Ă��Ă����̂ł����A��N���������Ă����̂����Ɍ����邱�Ƃɂ��܂����B����������Ƃ������Ƃ́A�܂��l���邱�Ƃ���ł̎��ł��B
�u���ׂĂ̌����͔�łɏW��v�Ƃ������Ƃ���ɓ��ɒu���A�ǂ��ڂ̑O�̓y�Ɍ����������ȑO����l���Ă��܂����B
�����čs�������͓̂y�̐������_�B
�u�y���ĉ����H�v���Č����đ����ɓ����邱�Ƃ��o��ł��傤���H
�ȒP�ɂ����A��̕����������̂Ǝ��R�E�̏z�ŏo���Ă����L�@���������肠���A�s�����������̂ł���܂��B
����͌�������Ă��āA�y��w�Ƃ��đ��݂��Ă��܂��B
�����������{���ɉ��w�I�ɐ����ł�����̂ɍ��܂ŏo����Ă��܂���ł����B
���o�������Ƃ��ł����A���ꂪ�u�y�됶�����_�v�ł��B
���� �쎁�ɂ�闝�_�œ������_�Ƃ������܂��B
�����u�y�̐S�@�y�̕����v�i����Њ��\��łɂ���ɓ���Ȃ��j�ȉ�����
*********************************
�P�j��{����1�@�@�L�@��(���n��L�@���Ȃ�тɊܐ����L�@������)�́A�t�F�m�[���܂���/����уt�F�m�[���I�o��̂��鉻�������܂ޔ�������ӎY����Y������邱�Ƃɂ��A�}���Ɍ����A���q���A�ÏW�A�k���A�d�����A���啪�q������Y��������B
�t�F�m�[���I�o��̂��鉻�����ɂ́A���R�̂��ƂȂ���A�t�F�m�[���I�o��̂���_���y�f���܂܂��B�܂��A���̊�{����1�ɂ�鐶�������L�@�����n�t���Ő��������y�됫���D�ł���A�܂����y���엿�ł���B
�Q�j��{����2�@�@�O�L�����ɍۂ��A���������ꂽ�]�_���𑽗ʂɊ܂ޕ������K�ʂɓY�������A���A���̂��߂̏d�k����������N����B
��{����2�́A�y��̐��������ł���B�܂��A���������ꂽ�]�_���𑽗ʂɊ܂ޕ����Ƃ́A�n�k�̕��ϑg���Ȃ����͂���ɋ߂��g����L���镨���ł����āA���A�G�l���M�[�I�ɕs����ȏ�Ԃɂ���]�_���������B���������āA�V�R���A���������킸�A���R�⎿�Ȃ����͗���⎿�̃K���X��Ō`�����D�܂����B
************************************
���ꂪ���_�̊�b�ł��B
���̗��_���瓱���o�������@�ɂ��A��ł���������ł��낤���Ƃ���������܂��B
���̗��_�ɂ͓y�Ɛ��Ɠy��ۂɍz���̊ւ��܂ł�����Ă���܂��B
���͂��̗��_��p���邱�Ƃɂ��A���܂��܂Ȏ����o���邱�Ƃ��킩���Ă��܂������A
���͓y�̐��ɁA��ł��������邱�Ƃɂ̂݃|�C���g���i��܂����B
������������Ă������̂����A�O�앨�����n�t�ł��B
���A�Ƃ������t�͍ŋ߂ł͗ǂ������悤�ɂȂ�܂������A�Ȃ�H����n�܂�܂��B
********************************************************************************
���A�Ƃ́H�t�F�m�[���Ƃ́H
�y��L�@���Ɠ����Ӗ��ŗp�����邱�Ƃ����邪�A�Ƃ��ɓy�뒆�œ��A����̂��y�됶���ɂ���ĕ����E�č������ꂽ�ÐF����`�i�R���C�h��j�̍����q�������i���A�����j���������Ƃ������B���A�͋@�\�I�Ȗʂ���́A�h�{���A�i�y��������ɕ�������₷���{���������ƂȂ�j�ƁA�ϋv���A�i�y��������ɕ�������ɂ����y��̕�������ǍD�ɕۂƂƂ��ɗz�C�I����ێ�����j�ɑ�ʂ����B���w�I�i�n�𐫁j�Ȗʂ������A�_�A�t���{�_�Ȃǂɂ���������B
�@���A�̖����Ƃ��ẮA�h�{���A�ɂ��앨��y��������ւ̗{�������A�ϋv���A�ɂ���c���̌`���A���A�_�ɂ��b�d�b�i����u���e�ʁA�z�C�I�������e�ʂƂ������j��ɏՔ\�̑���A�t���{�_�ɂ��S�E�A���~�j�E���̃L���[�g���ȂǁA���ɑ���ɂ킽��A�앨�̐���ɓK�����y�������Ă��������ŁA����߂ďd�v�Ȃ��̂ł���B�y�뒆�����A���ێ��E���������邽�߂ɂ́A�L�@���̎{�p���Δ��앨�̓����Ȃǂ��L���ł���B
�@�Ȃ��A�ŋ߂ł͗L�@���𑽗p���Ă��锨�ŁA�엿�̌����������Ƃ������ۂ��݂��Ă���B����Ȕ��ł́A�y��������̊��������߂�K�v�����肻����
�t�F�m�[��(phenol�Abenzenol)�́A���ʊG���̂悤�ȓ��L�̖�i�L�������L�@�������ł���B�F�����������̂ЂƂŁA�퉷�ł͔��F�������B�x���[�������f���q�̈���q�h���L�V�����ɒu�������\�������B�a�����ΒY�_�i��������j�B�L�`�ɂ́A�F���������f���q���q�h���L�V���Œu�������������S�ʂ��w���B�����ɂ��Ă��t�F�m�[�������Q�Ƃ̂���![]()
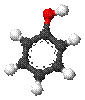
���[�����d�q�}���ق�蔲��
���A�ɂ���
|
�n�\�ɍL�����z���A�����̍�p���w�E����Ă���"���A"�́A���̋@�\�̌������قƂ�Ǖs���ł��������߁A�����Ƃ��Ă̊��p���킸���ȕ���łȂ���Ă����ɂ��������܂���B�Ⴆ����n����"���A"�͐_�o�ɂɌ��ʂ�����Ƃ��A�܂��ʂ̒n����"���A"�͓��A���̐���𑣐i����A�Ȃǂł������A"���A"��ʂ����̂悤�Ȍ��ʂ������Ȃ����߂ɁA�قƂ�ǂ������p�̂܂ܕ��u����Ă��܂����B �������Ȃ���A���A�����w��Ȃǂł�"���A"�����@�\�ł��邱�Ƃ͑����̌����҂��F�߂Ă��܂����A���A�̍\����g�������G�Ȃ��ߌ����̗��j���A���ł������������������Ă��܂��B |
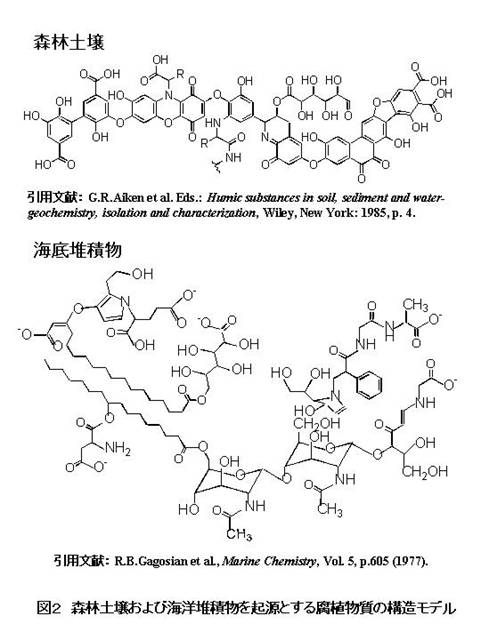
�L�@���̕��A�ւ̕ω�
|
�@�L�@���̕��A�ɕω�����ߒ�������"���A"���璊�o����ƁA�����̒��o�����͏�L"���A"�̋@�\�Ƃ���鏔���ʂ������Ɏ����܂��B�������͂��̕�����"���A�O�앨��"�ƌĂ�ł��܂��B |
|
�A�Ƃ��낪�A�L�@�����t���{�_�E�t�~���_�ɂ�����ω��o�H�����ǂ�������I�ŏI�Y���Ō]�_���̖��@�����ܗL��������������"���A"�̋@�\�Ƃ��������S�������܂���B |
|
|
���̂��Ƃ��畅�A�O�앨�����J������܂����B
���̕��A�O�앨���͕ی����̌������u�H�ށv�Ƃ̕��ޔ���ɂ���܂����B
���ꂩ��A���ŋߗL�������𒊏o�������A�O�앨�����n�t���J������܂����B
���̐��n�t�ɂ͗L�@���Z�x���P�D�W���ł��B
�咰�ۂ��S���܂܂�Ȃ��̂ŁA���邱�Ƃ��Ȃ��ۑ����ɗD��Ă��܂��B
���A�O�앨�����n�t�͕ی����̌������u�����������v�Ƃ̕��ޔ���ɂ���܂����B
���A�O�앨�����n�t�̓�������э�p
�@���������̏W���̂ł���@���@�L�@���̕��A�����i�A�����ہE���A���ւ̐������i��p�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�A���j�Q�����̌Œ艻�E�s������p�@���@�j�Q�����̃C�I�����ƃL���[�g�\���ւ̎�荞�݁@�@�@�@�@�@�@
�B�����̕ΐ����C���ە��тɃ��B�[���X���ɑ���}���E�ŋی��ʁ@���@�����R�ۓ��̗}���E�ŋۍ�p
�C�זE�����̐��̖��ɑ��铧�߁E�Z�����ɗD��Ă���@���@�d�ʍ��ێ���p�A��`�q�ی�(�t���[���W�J�������\)��p�Ȃ�
���A�O�앨�����n�t�̊��p
�P�D�y�뒆�ɐ�������������̊������A�܂萶�����̉��P��}��܂��B
�y��̐���������Ƃ��ɁA���w���A�������A�������ɕ������܂����A�����������P����Ȃ���Ή��w���������������P����܂���B
��{�I�Ɍ������@�\��L����A���i�_�Y���j�ɂ͗L�@���i�͔�Ȃǁj�̎{�p�͕s�v�ł��B
�L�@���̕K�v���͓y�뒆�ɐ�������������̂��߂ł��B
�y��������͗L�@�����h�{���A�G�l���M�[���Ƃ��邱�Ƃő��푽�l�ɑ��B���Ă����̂ł��B
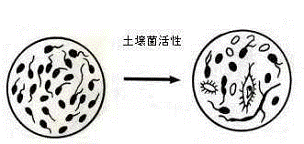
�Q�D�y�������������������Ɠy�뒆�̗L�@����ۑ����邽�߂ɕ��A�����i�s���܂��B
���ꂪ�������̉��P�ł��B�L�@�������A�����邱�Ƃœy�낪�d�ׂ�тсA�c�������i�s���܂��B
������L���[�g�\���ɂ��c�����ƌ����܂��B
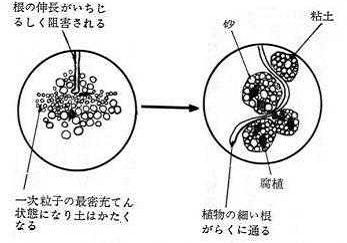
�R�D�L���[�g�\���̔��B�Ɠ����ɃL���[�g���ɖ��@�C�I������������荞�܂�܂��B
���ꂪ���w���̉��P�ł���A�y��̎������サ�܂��B
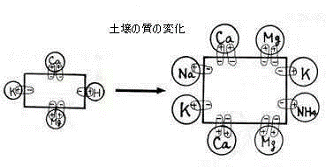
�i�Q�l�����j
�L���[�g
���w�ɂ������L���[�g (chelate) �Ƃ́A�����̔z�ʍ��������z�ʎq�ɂ������C�I���ւ̌����i�z���j�������B���̂悤�ɂ��Ăł��Ă����������L���[�g���̂ƌĂԁB�L���[�g���͔̂z�ʎq�������̔z�ʍ��������Ă��邽�߂ɁA�z�ʂ��Ă��镨�����番�����ɂ����B������L���[�g���ʂƂ����A�L���[�g���̂łȂ����̂ɑ�10��10��{�Ƃ������I�[�_�[��[�v�o�T]�z�ʂ̕��t�萔�̒l�����シ��B���q�����̍\���ɂ���Đ��������Ԃ����������ގp����A�M���V����́u�I�̒܁v�ɗR������B
����
�����i���������Acomplex�j�������������i��������Acomplex salt�j�Ƃ́A�z�ʌ��������f�����ɂ���Č`�����ꂽ���q���������̑��̂ł���B���`�ɂ́A�������q�𒆐S�Ƃ��āA���͂��z�ʎq�����������\���������������i�������́j���w���B�w���O���r�����N�����t�B���Ȃǐ����I�ɏd�v�ȋ����L���[�g�����������̂ł���B�܂��A���S�����̎_�����Ɣz�ʎq�̓d�ׂ��ł����������Ă��Ȃ��C�I�����̍��̂����C�I���ƌĂ��B�������̂́A�L�@�������E���@�������̂ǂ���Ƃ��قȂ鑽���̓����I�������������߁A���݂ł����ɂ�����Ȍ������s���Ă��镨���Q�ł���B�E�F�L�y�f�C�A�����p
��łƂ͉����H
�T���v���������̂ł����A�������ꂽ�����ł͋����R���̒ʏ���ʗv�f�ƌĂ����̂����o���ꂽ�Ƃ̕��Ă��܂��B�_�n�Ƃ�����������A�엿�Ȃǂ��琄�@�����͕̂s��������̏W���̂ƁA�ΊD�ɂ���Ր����ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B
�E���ΊD�i�g�p���Ȃ����j�E�E�E��@���ΊD�{���@�b���n�{�g2�n���b���i�n�g�j2�����ΊD�@�
�@�@�@�@�@�@���g�p���Ȃ����R�E�E�E�y���ł��Ȃ�B���ʂƂ��ĕޏ�ŋN�������w����
���ǁi����j��������@���ΊD�{���������{�z�C�ہ{�ԓy�@
���@�ޏ�ł����i���ΊD�{�ؘm�{�S�y�j�œ������
�����^�������@�@���@���ΊD�{���{��C���̂b�n2
�ޏ�ł́@�@�@�@�@���@���ΊD�{���������_�J���V�E���ƃA�����j�A�̔엿�Ƃ��Ă̌��ʁ@�@�@�@�@�����҂��Ă���悤�ł��邪�A���ۂɂ͏��ΊD�{�L�@��(�ؘm�Ȃǁj�{�y��i�S�y���j�̎���Ɠ����̍H���Ɛ���n���T�O�p�ʂ̏��ɐΊD���̊�Ցw�ƂȂ��Ă��鎖�������B
�L�@�ޏ�ł͑�ʂ̗L�@�������Ă����āA�t�Ɍ����ɂ����Ȃ��Ă���B
���̔�łɑ����A�O�앨�����n�t�̓�������э�p�ɂ��A�s��������͕�������L���[�g��荞�݂��s����B
�L�@���ɑ��Ă͕��A����i�߁A����ɕ����L���[�g�Ɏ�荞�܂��B
��L��p�ɂ���ł̉����ɂȂ���B

�ȈՎ���
���͓������A���������t��A����ɕ��A�O�앨�����n�t������Ɛ����Ŋ�{�����P���N����
�������Ă��܂����B
���R�E�ł͔�������X�s�[�h���������߁A���Ƃ���łƂ����ǂ��������Ă��܂��̂������B
���ۂ̕ޏ�ɂĂǂ��������ʂ��łĂ���̂��́A�������̌���ɂČ����ׂ��ł���B
���낢��ȏ����̈Ⴄ�Ƃ���ŌJ��Ԃ�����Ă݂āA��舵���̃��[��������Ă����ׂ����낤�B
���R�͔|�ڍs�O�̏����i�K�Ƃ��Ĉ����ɂ͂������@���Ǝv����B
���R�͔|�̕ޏ�ł̈����͂�莩�R�ɋ߂����߂���Ɍ��ʂ��o�Ă���Ƃ������Ƃł���B
�͂����āA����ȂɊȒP�ɔ�ł͉����ł�����̂��낤���H
�����{���ɂ��ꂪ�\�ƂȂ�A�ڍs���Ԃ̒Z�k�ɂȂ�A�����I�ȕω����N����̂ł͂Ȃ����낤���H�����̃T���v���̎��W�ɂ����ʂ̏W�ς��͂���A��萸�x�̍������p�̎d���������Ă���B
���N���̎������s�����Ƃɂ��Ă���̂����A���܂�̏Ռ��Ɍ��ʂ�҂����Ɍ��J�����B
�ӌ������߂�������Ȃ���킩��Ȃ��̂����A���̎��_�ł̈ӌ��������B
���ɋC�ɂȂ�̂��A���R�͔|�Ƃ̐������ł���B
���R�ȊO�ɉ����ɂ�����Ȃ��Ƃ����v���ƁA�������ł��邩�킩��Ȃ���łƂ̂͂��܂ŔY�̂����A�������L���邱�Ƃł���������������̂Ȃ�Ǝv��������ł���B
���o�͒|�Ȃǂ̎��R�L�@������ɂ��B
���̎{�s�ɂ�肻�̏z���o���オ��̂ŁA�g��������Ƃ������̂ł͂Ȃ��B
�������̌��ʂ̂قǂɂ�萔��̎d�l�͒v�����Ȃ��̂�������Ȃ����A�z�����o���オ������̂ł����āA�ˑ�����Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ����̂Ǝv���Ă���B
���ݕ����y��ł��錋��
|
�y���_�炩���Ȃ�A�ɏՍ�p�������Ȃ�A�ې��������A���͂����ǂ��Ȃ�A�����F������B �L���[�g�Ɏ�荞�܂ꂽ�����̓C�I��������Ă���A���ł��o������\�Ȕ엿���ƂȂ�B ���A�O�앨�����n�t�̎{�p ���A�O�앨�����n�t���Q���{�ɔ��߂����̂�ޏ�Ɏ��������ŗǂ��B ���悻�Q�T�Ԃقǂœy�̒c���������i����A��ł����������B �y��������������������̂ŁA�l�I�Ƀ}�C�i�X�̎肪����Ȃ����莩�R�̏z�̏�Ԃ��ێ������B���ʂ̔��f��͑咰�ۂ̗L���łł���B ���R�̏z�Ɍ��������߂̋N���܂Ƃ��čl���邱�Ƃ��ł���B �N�ɂł��Č��ł�����@�Ƃ��Ċm�����邽�߂̌��؎��Ⴊ�K�v�ł��� |
���̊֘A����

�������ɔ��ʂ����A�O�앨�����n�t����ꂻ�̂܂܋�����Ĕ��N��̏�ԁB
���̐��͓y��ۂ̓����ɂ��A���Ԍo�߂��Y��ɂȂ��Ă���B
���R�̐��Ɠ������ő咰�ۂ����Ȃ��̂ŕa�C�ɂȂ炸���C�Ɉ���Ă���B
��ʂ̃t�������������悤�ɂ��Ă��邾���������ł��B
���������ĎM�ɒu�����܂܂ɂ��Ă�����Ȃ��Ŋ�����тĂ����B
���̂��Ƃ��Ǝv������A����Ȃ��Ƃ��ł���̂��H
���A�O�앨�����n�t�������܂܂��������A�{�Ɉ��܂��Ă��邾���ł��̗����ł���̂������ł��B�����������ɂ�镅�s�����ł͂Ȃ����I
��N�č��ɗ��p���ꂽ�_�Ƃ���ł͂Q�����̎��ʑ������������ł��B
���N��J���ꂽ�ؑ��H������̊�Ղ̃����S�͂P�N�ŏo���邻���ł��B
�i���ꂪ�Ռ��ł����j
�悤����ɁA�ώ_���\���ǂꂾ�����邩�H��͂����ɂ��邻���ł��B
�^�C�ł���𗘗p�����엿�H�ꂪ�ғ����Ă���A����ɐ��̏ɂ����������Ă̈˗������Ă���̂��Ƃ����B
���A�O�앨�����n�t�̊J����Ɋւ��ẮA����݂Ȃ��K�v�Ǝv����̂Ȃ�Ό��J���܂����A�����Ə�~�����ƌ����Ȃ�Ό��J�����������Ă���������Ƃ̗��������Ă��܂��B
���e���悭�������Ȃ��܂܂ɂ������ȕ����ɂ����Ȃ����߂ɁA����͊J������邱�Ƃɂ��܂����B
���͍���̎��R�͔|�ɕK�v�ȋZ�p�ł͂Ȃ����Ǝv���A�Љ�܂����B
�y�됶��(����)���_ (���� �쒘 �|���r�R���̉͂�n��Ȃ����߂Ɂ|�@��y�̐S �y�̕����v ����Њ�)��蔲��
�P�j��{����1�@�@�L�@��(���n��L�@���Ȃ�тɊܐ����L�@������)�́A�t�F�m�[���܂���/����уt�F�m�[���I�o��̂��鉻�������܂ޔ�������ӎY����Y������邱�Ƃɂ��A�}���Ɍ����A���q���A�ÏW�A�k���A�d�����A���啪�q������Y��������B
�t�F�m�[���I�o��̂��鉻�����ɂ́A���R�̂��ƂȂ���A�t�F�m�[���I�o��̂���_���y�f���܂܂��B�܂��A���̊�{����1�ɂ�鐶�������L�@�����n�t���Ő��������y�됫���D�ł���A�܂����y���엿�ł���B
�Q�j��{����2�@�@�O�L�����ɍۂ��A���������ꂽ�]�_���𑽗ʂɊ܂ޕ������K�ʂɓY�������A���A���̂��߂̏d�k����������N����B
��{����2�́A�y��̐��������ł���B�܂��A���������ꂽ�]�_���𑽗ʂɊ܂ޕ����Ƃ́A�n�k�̕��ϑg���Ȃ����͂���ɋ߂��g����L���镨���ł����āA���A�G�l���M�[�I�ɕs����ȏ�Ԃɂ���]�_���������B���������āA�V�R���A���������킸�A���R�⎿�Ȃ����͗���⎿�̃K���X��Ō`�����D�܂����B
�R�j����������(��{����1,2)�̓L���[�g�\����L���ɏՍ�p�������B
�y��یQ�����t�F�m�[���n�̐������܂������ꍇ�A�����������́A���L���[�g�\���̔��B��������ƂȂ�B�L���[�g�\���Ƃ́A�S�y�z������ł��p��ł���A�͎��I�ɂ͔n���`�̓����ɁA+�A-�A�̓d�ׂ����݂���\�����w���B���������āA�����������ɃL���[�g�\�������B���邱�Ƃɂ��A�C�I���������̃R���g���[�����\�ƂȂ�ق��A�L���[�g�ɂ��ɏՍ�p���@�\���邱�ƂƂȂ�B
�S�j�������́A�y��������Ƃ��̊O�G�Ƃɕ������B
�y��������Ƃ́A�y��̐����Ɋ֗^����������̑��̂��Ӗ�����B�����āA�y��������́A���̂Ƃ��Ă̓y��یQ���܂�����̂ł���B�{���̐������܂������y��������ɂƂ��ẮA�y��̐����Ɋ֗^�����Ȃ��������́A���ׂĊO�G�Ƃ��Ă̑��݂ł������肦�Ȃ��B�\����������A�{���̐������܂������y��������́A�y��̐����Ɋ֗^�����Ȃ��������Ƃ́A���������Ȃ����ƂƂȂ�B
�T�j�������ɂƂ��āA���ȈȊO�͑S�ĊO�G�ł���B
�����ł������ȂƂ́A�̂Ƃ��Ă̎��ȁA�푮�Ƃ��Ă̎��ȁA�Q�̂Ƃ��Ă̎��ȁA���Ӗ�����B���������āA�y�됶���Ɋ֗^���鐶������(�t�F�m�[���n)�������y��یQ�ɂƂ��ẮA�y��یQ�ȊO�̔������A�Ⴆ�Α咰�ہA���s�ہA�a���ۂ͑S�ĊO�G�Ƃ������ƂɂȂ�B
�U�j��ӎY��(���啨)���A���Ȃɑ��鐬�����i��p�A�O�G�ɑ���R�ۍ�p��L����B
�����W�ɂ���(��)�������܂߂����Ȃł����āA���y�됶���Ɋ֗^���鐶������(�t�F�m�[���n)�������y��یQ���̂Ƃ��Ă̎��Ȃ���Y�o������ӎY���́A�y�됶���Ɋ֗^����������ȊO�̔������ɑ��āA�R�ۍ�p�������B�܂������ɁA�Y��ӎY���́A���Ȃɑ��鐬�����i��p������B
�V�j�������͊��̕ω��ɉ����āA�������܂�ς��鐶���ł���B
���������ƈقȂ�A�P�זE�����ł���ۗނɂƂ��ẮA�O�G���ω��ɉ����Ď��Ȃ̐�������(��Ӌ@�\)��ω���������A�����I�ɐ����̂т邷�ׂ������Ȃ��B�܂�A�������͂ЂƂ̊������ɑ��āA�ЂƂ̐������܂őΉ����邱�Ƃɂ���Ă̂݁A�����I�ȑ�����ۏႳ���̂ł���B
�W�j�y��یQ���̂Ȃ�тɎ푮�Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�Q�̂Ƃ��ĂƂ炦��B
�y��������̂�����Ƃ��ē��肳�ꂽ���̂́A�S���̈�ɂ������Ȃ��B�������T�C�Y�ȉ��̓y������������l���ɂ����ƁA�S�����m�ł���A�Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B���������āA�������T�C�Y�ȉ��̔����������܂߂āA�Q�̂Ƃ��Ď�舵�����Ȃ����ƂƂȂ�B�܂�A�������T�C�Y�ȉ��̔���������͂���ɂ́A���炩�̃G�l���M�[�������s���ł���A�������͂��̌��ʁA�Y�G�l���M�[���x���ł̐������܂Ɉڍs���Ă��܂�����ł���B
�X�j�D�C����(�ʐ����C���ۂ��܂�)�Ƃ́A���q���_�f�Ȃ����͗V���_�f�̋�������A�����\�Ȕ������ł���B
�ۗނ̔��ˊ�(��R�O���N�O)�ɂ́A�V���_�f�͑��݂��Ȃ������B���������āA�D�C���ۂɂƂ��Ă̖{���̐������Ƃ́A�ΐ����C���ۂƂ̋����W�̒��ŁA���q���_�f�̋�����������ł���B
�P�O�j�y��یQ���O�G���ω��ɉ����āA�t�F�m�[���n����t�F�m�[���n�̑�Ӌ@�\������B
�t�F�m�[���n��Ӎ�p�Ƃ́A�y��یQ���y��̐����Ɋ֗^�����鐶�����܂�����ꍇ�̂���ł���A��t�F�m�[���n��Ӎ�p�Ƃ́A�y��یQ���y��̐����Ɋ֗^�����Ȃ��������܂�����ꍇ�̂���ł���B���������āA�t�F�m�[���n��Ӌ@�\�������y��یQ�́A�G�ۗނƂ͋��������Ȃ��B����A��t�F�m�[���n��Ӌ@�\�������y��یQ�́A�G�ۗނƋ������邱�ƂƂȂ�B�����ʂ��炢���A�t�F�m�[���I�o��̂��鉻��������ӎY�����Ɋ܂܂�邩�ۂ��Ńt�F�m�[���n�A��t�F�m�[���n�ɋ敪�����B�������Ȃ���A�t�F�m�[���n�A��t�F�m�[���n�Ƃ����Ă��A���҂̊W�͘A���������̂ł���A�܂��A�����Ƀt�F�m�[���n�ł���Ƃ��A��t�F�m�[���n�ł���Ƃ��A�Ƃ�����Ԃł͓V�R�ɂ͑��݂����Ȃ��B�܂藼�҂̊W���A��萳�m�ɕ\������Ȃ�A���t�F�m�[���n�ł��邩�A����t�F�m�[���n�ł��邩�A�Ƃ������ƂɂȂ炴������Ȃ��B
�P�P�j�y��یQ�ɂƂ��Ă̖{���̐������܂́A�t�F�m�[���n�̂���ł���B
�y��یQ�̔��ˊ��ɂ́A�V���_�f�͑��݂��Ȃ������B���̂悤�Ȋ������̒��ŁA�ΐ����C���ۗނ����˂��A�Y�ۗނ��D�C���ۗނƗV���_�f�̑��݂��Ȃ��������Ńy�A��g�ނ��Ƃɂ��A�ΐ����C���ۗނ̑������ۏႳ�ꂽ�̂ł���B����A�����ɂƂ��ẮA�Y�����̔��ˊ����{���̐������ł���A���̖{���̐������Ŕ������鐶�����܂��A�{���I�Ȃ���ł���B���̈Ӗ��ɂ����āA�܂��y��یQ�̒�`���炵�āA�y��یQ�ɂƂ��Ă̖{���I�Ȑ������܂́A�y�됶���Ɋ֗^�����鐶�����܁A�܂�t�F�m�[���n�̂���A�Ƃ������ƂɂȂ炴��Ȃ��B